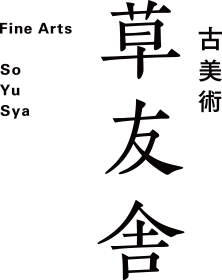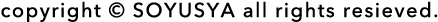2024.7/10
絵葉書

知人からある古い本を借りたら表紙が人勝残欠雑張だった。
四十年近く前、初めて東京国立博物館に行った折に売店で販売していた人勝残欠雑張の絵葉書を、その作品が何とは知らずに買ったことを思い出した。
童子に仔犬らしき動物が慕っているような無邪気な絵、中国風な色合い、新年を言祝ぐ十六の文字は、気持ちを朗らかにさせてくれる。
その時に十数枚ほど買ったのに、手紙を書き損じることも多いので投函する以前に減ってしまう。
東博を訪ねるたびにこの葉書を補っていたが何年かして見なくなり、もう手元にはない。
一枚残しておけばよかった。
人勝残欠雑張は染織品ということだが、正倉院展には二度しか行ったことがなく、実物を見たことがない。
調べてみると、人勝残欠雑張は1981、1990、2009年に東博での特別展に出陳されていた。
遡って計算すると、私が初めて東博に行った年は1991年なので、1990年に作られた葉書の在庫がなくなるまで売られていたのではないかと思う。
2009年に見られる機会を逃していた。